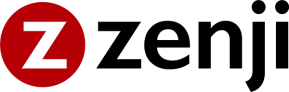「自然の仕事」の特徴は、自然の物理的・化学的作用により生まれたものであり、人間や動物が関与していないということだ。つまりそこに作品意識などが入り込む隙間はない。錆びによる変化、剥がれや褪色といった経年の痕跡など、時間と作用が共に生み出した造形である。
作為という点では、人間の意図が介在していないので、このカテゴリはシリーズの中で最も作為から遠い位置にある。
自然が作り出した仕事の例

雨が作り出した模様。雨樋があるがほとんど役に立っていないようだ。雨樋から滴る水が壁に模様を描き出した。しかし、なぜこんなにくっきりとした模様が生まれたのだろうか。また、下まで流れ落ちず、途中で止まっているところも良し。

鉄錆のようなものが壁に浮かんでいる。これは内部から出てきたものなのか、外部から付着したものなのか。白く塗りつぶした部分はキャンバスのようでもある。さらにその左側には黒い滴りもある。これは塗料なのか? それともタールか何かだろうか?

青と白と錆色で構成されたトタンの壁。わざとエイジング加工をしたんじゃないかと思わせるような絶妙な配色。文化遺産として保護したいくらいだ。

ペンキのピーリングにより生まれた美しい配色。何層にも塗られたペンキが部分的に落ちてできたのか、それともペンキで何かが描かれていたのか。汚れやヒビと共に複雑なテクスチャーが浮かび上がっている。

風で揺れる木が壁面を引っ掻いて生まれた弧状の模様。赤瀬川原平はこのようなものを植物ワイパーと呼んだ。これは木がスクラッチした後で剪定が行われたようで、高い部分にもその模様が残っている。風が描いた絵画と考えると詩的な気分になる。

壁に残る同心円状の模様。これはヒントがないので全くの想像になるが、何かが壁にぶら下がっていたのではないか。そしてそれを留めていた画鋲のようなものを中心としてクルクルと回転した。そしてこのような模様ができたのではないだろうか。

旧築地市場内で見つけたマンホールカバー。場内には荷物を運ぶためにターレと呼ばれる小さな運搬車が走り回っていたが、このターレに使われていた発泡ウレタン製のノーパンクタイヤが硬かったようだ。長年ターレに轢かれた結果、このような凸凹のマンホールカバーに育ってしまったのだろう。

京都の太秦撮影所内にあったマンホールカバー。時代劇の中にマンホールカバーが映り込んでしまうとまずいので、ここで撮影をする時には上から砂を被せて隠しているのではないだろうか。そしてこんな感じのマンホールに仕上がってしまった。

鎌倉で見つけたいい感じの壁。しかしこれはまったくの偶然ではなく、経年変化も計算に入れて壁を塗っているのかもしれない。京都を歩いている時にもそのようなデザイン的意図を感じることがある。

家の裏手にある居酒屋の入り口舗装面で発見。落雷のようなひび割れ模様に惹かれて撮影。30cmぐらいの小さなスペースなので、このようなものに気を取られる人は誰もいないだろう。

建物の壁面が異様に盛り上がっていた。裏原宿であればデザインかなと思うが、ここは足立区である。古いGoogleマップの写真ではヒビが入っているのが確認できた。つまり経年変化で膨らんできたところにさらに吹きつけ塗装を行なったということのようだ。

山手線の駅のホームの広告看板。この看板はいくつか並んでいて、広告の切り替え時期にはこのような状態が出現する。それぞれの模様が違い、いつも電車の中からそれらの抽象画を鑑賞している。